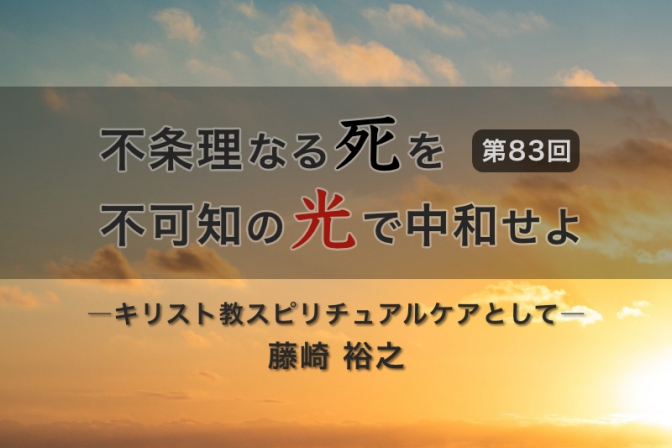不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(83)
キリストの名前を使って悪霊を追い出す、というのは私にはなじみのない行為である。しかし、よくよく考えてみると、大変重要なことではある。癒やしを頼まれたというのは数回しかなかったが、もちろん、頼んだ相手はキリストの名前によって癒やしを求めているのであって、「私の力」に信頼してくれたわけではない。
残念ながら、牧師時代に所属していた教団にはいわゆる「癒やしの手順」というものがなかった。教団としては、牧師が癒やしを行うことに好意的ではなかったように思う。癒やしが奨励されることもないので、勉強会やら講習など全くなかったのである。その代わりといっては何だが、教会に相談を寄せる人々には親切に対応するように指導されていたように思う。
「よろず相談承ります」というわけではないので、相談に来たり、電話をかけてきたりする人は年に数人程度ではあったが、まるっきり「頼まれごと」に無関心だったわけではない。あるいは、何でもかんでも「福音宣教!福音宣教!」で、聖書講義に時間を費やしていたわけでもない。
癒やしを頼まれても、結局のところ「私にはできません」ということでお断りしていた。北海道江差町にある教会を担当していたときに(函館から毎日曜日に通っていた)、ブラジルから里帰りした親子が礼拝に出席していた。礼拝後に子どものアトピーを癒やしてほしいとお願いされた。カトリックの信者であったので、南米のカトリック教会ではそういうことをやっていたのかと思いつつも、「私の教団では癒やしはしていません」と答えるしかなかった。
全くの偶然というか、まあ、それも神の思し召しなのだろうが、本当にたまたま私の妻が同行していたのである。妻は小児科医で、日常的にアトピーの治療をしている。私はすぐさま親子に「ここに小児科のお医者さんがいるので診てもらいましょう」と勧めることができたのであった。
近代以前の聖職者は、ある程度は医療に精通していたらしいから、宣教と同時にキリストの名による病気治療も可能であったし、大抵の聖職者はそれを実行していたらしい。宗教と医療が分離したのは近代以降なので、かつては聖職者の訓練の中に医療が含まれていたとしても当然のことであっただろう。今の時代なら医者を同行して地方宣教に行くというのもありなのだろうが、残念ながら昔に比べるとクリスチャンの医師が少なくなったので不可能になりつつある。
教会と癒やしは身近なテーマになり得るが、しかし、教会で癒やしが実現しているのかどうかは私には分からない。教会で癒やしを行っていると言ったら、怪訝(けげん)な顔をされるのがオチであったし、癒やしを行うと公言している牧師がいたら、私は躊躇(ちゅうちょ)なく距離を置いていた。
もちろん、癒やしを行う牧師や神父は、それが本業ではないのだから経済的な目的はない。あくまでも福音宣教の一環として行うだけである。私は最初から全く不可能だと思っていたから、その是非を考えたこともなかったが、牧会の途上でその必要を感じて努力の末に癒やしを身に着けた人もいるのだろう。それはそれで尊重したいと思う。
ヨハネは、「お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないので、やめさせました」とイエスに報告した。「私たちに従わない」というのが何を意味するのかイマイチはっきりしないのであるが、弟子たちの監督下に身を置かないということなのかもしれない。イエスの名を使う以上は仁義を守れということか。
さらに言えば、イエスの名によって悪霊を追い出している者が、無料奉仕であったかどうかも分からない。良心的な解釈をすれば、かつてイエスによって悪霊を追い出してもらった人が、つまり自分にはイエスによって神的な力が宿っていると信じた人が、悪霊を追い出していたのかもしれない。自分にしてもらったことを、他者にお返ししているというのはあり得る話である。
大切な点は、イエスの名によって悪霊を追い出しているということである。イエスの名は悪霊に打ち勝つということだ。自分の力ではなく、悪霊に打ち勝つイエスの名による力なのだ。イエスの力を借りて、あるいは、イエスの力を身に帯びてということだ。大体にして私には全くそういう感覚はなかったのだが、それはそれで立派な信仰だというしかない。
私は「聖書」を重んじる教団に属していたので、何でもかんでも聖書の言葉で解決しようとしていたように思う。もちろん、聖書の言葉には力があると信じているなら、聖書の言葉で何でもかんでも解決しようとするのは立派な心がけである。それでも、聖書の言葉なら何とかごまかせると思うのも「信仰者あるある」であって、まあ、私はそういう姿勢も歓迎する側にいるような気がする。それはそれで涙ぐましいほどの努力の賜物には違いないのだ。(続く)
◇