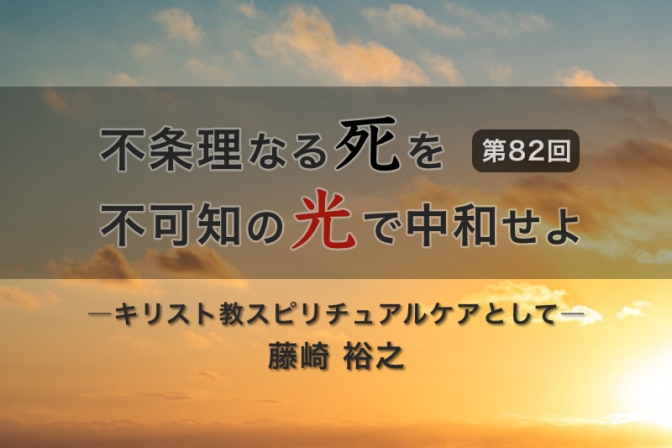不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(82)
選挙には行くのであるが、選挙に行かない人を批判する気持ちはみじんもない。25歳くらいのこと、かれこれ40年近く前のこと、正直言ってそれまで選挙に行くことはなかったし、選挙に行くことに何の価値も見いだせなかった。ある牧師から「みんなが選挙に行かないから自民党が勝利してしまう」と批判を受けた。その人にとっては、自民党が選挙で勝利することは明らかに悪であったように思う。
今に比べれば、自民党の政治というのも随分とマシであったような気もするが、確かに当時の私にとっても、自民党の政治はよろしきものではなかった。それでも選挙に行く気がしなかったのは、選挙に行かないことが自民党政治に加担しているのだという、その何かよく分からない論理に納得できなかったからである。
宣教に行かないというのも、これまたいろいろな意味で問題にされる。高知の田舎を出て、北海道で牧師人生を終えたというのは、確かに宣教に「行かなかった」とは言えない。言えないが、実際のところ、私自身としては伝道をしたとか、宣教をしたとか、そういう意識が全くない。それはなぜだろうかと考えるが、恐らく、誰かに言われるままに、そして誰かに用意をされた場所で、牧師をダラダラと続けていたからだろう。自覚も根性もないということである。
選挙に行かないと批判されるが、宣教に行かないというのも、確かに批判されるに値する。地方の教会で、いわば日本の果てで牧師をしたのは事実であるが、それがイコール宣教に行ったということにはならない。教会で牧師はやったが、地域の家々を個別訪問したということもないし、町内会には顔を出さないし、教会の門から一歩進み出てキリストを語るなどということもしていない。まして路傍伝道など考えたこともない。
全くもって情けない。なぜこのような情けない人生になってしまったのだろうか。選挙に行っても日本は変わらないと、しらけきった25歳の若者だった私、それと同じように、宣教に行ったとしてもうまくいかないと諦めていた地方の牧師、それは同根なのかもしれない。
何歳くらいの時であったか、選挙に行くようになった。選挙に行って政治を変えてやろうとか、自分が選挙に行ったら日本が変わるとか、そんな大それたことを考えたわけではない。どういうわけか選挙に行こうと思うようになったのだ。
宣教も然りであるのかもしれない。それは義務ではない。いや、確かに聖書にはそれが、信仰者のあるべき姿というか、当然のことと書いてある。行って世界の果てまで福音を伝えよと、イエス・キリストが命じておられる。それは否定できないし、行かなくてもよいという解釈は不可能だ。それでも私は、義務ではないように思う。
イエスによって助けられた名もなき人は、デカポリス地方に行って「イエスが自分にしてくださったこと」を言い広めた。言葉を変えれば、イエスによって自分の身に起こったことを伝えたのである。彼が伝えたのは、イエスの十字架と復活による救いではなかった。汚れた霊によって苦しめられた人生から助け出されたという顛末(てんまつ)を伝えたのである。そこには、整理された信仰理解があるわけではない。
それ故にといえば失礼ではあるが、自らをレギオンと名乗った彼は、伝道者や宣教者と呼ばれることはない。強いていえば、「証し人」ということになるだろうが、それでもやはり十字架と復活を経験していないが故に、この人は「証し人」として語られることもない。
わが人生を振り返って、イエス・キリストが私にしてくださったことを人に伝えるということがあったであろうか、といえばない。むしろ、そのようなことを避けていた。牧師としては当然のことであり、今でもそれは正しいと思う。牧師は自己宣伝をしてはならないのだ。という、教科書的な刷り込みが、まあまあ私には機能していた。それで良い。自己宣伝する牧師は好きではない。そういう話も聞きたくはない。
しかし、レギオンと名乗った人は果たして自己宣伝を繰り返していたのだろうか。真意は分からないが、彼の行動がしっかりと聖書に書き残されていることに、大きな意義を私は感じている。この人は自分が伝道、宣教をしているなどと思いもしなかったであろうし、その義務も感じていなかったであろう。ただ、自分がイエス・キリストから受けたこと、悪霊から解放され、墓場の生活から、全く新しい人生へと出発した、ただただ、その事実を伝え歩いたのだ。私には、それがうらやましい限りなのだ。
◇