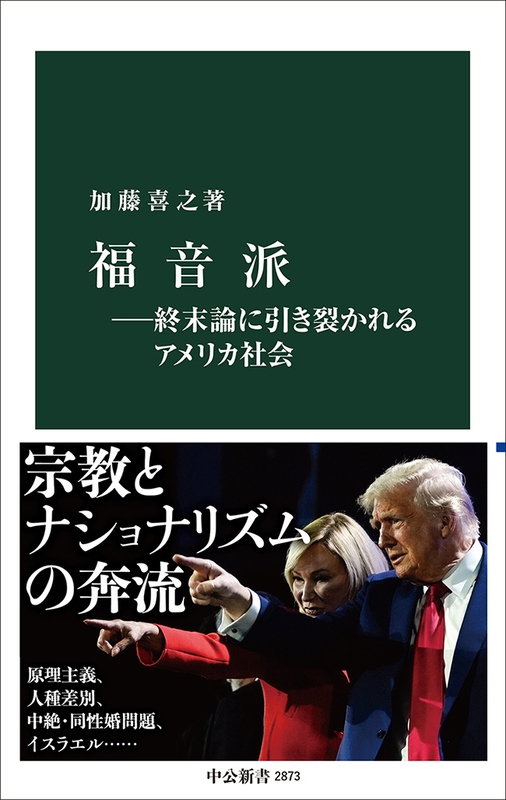本書は、福音派の入門書ではない。米国の福音派が、歴代の大統領とどのように関わってきたかを詳細に伝える専門書といってよいのではないだろうか。その意味では、言い方の良し悪しは別として、プロテスタント主流派(リベラル派)に身を置く、一介の牧師である私にとっては、自分が福音派について学んでおくべきであろう範囲を、はるかに超えた内容であったように思う。
本書には膨大な人名の記載があり、恐らくそれは、米国の福音派についてある程度の知識を持っている人であっても、手を焼くのではないだろうか。このように、本書は福音派の教義を詳細に伝える書ではなく、米国における福音派の人脈と、そのロビー活動、また逆に、政治家の福音派に対する戦略を、1950年代から今日に至るまでを、年代別に、具体的な人名を伴って著している書と見ることができる。
かといって、教義に関する記述が全くないわけではない。例えば1970~80年代に、「キリスト教再建主義」が登場するまでの福音派における「救い」の定義は、以下のようにまとめられている。
多くの人たちにとって、それは死後、地獄に行かずに天国に行けるということを意味していた。したがって、重要なのは来世の救いであり、現世は永遠に続く死後の世界――天国であれ地獄であれ――の準備にすぎず、キリスト教徒はできるかぎり福音を多くの人に伝え、それにより彼らを地獄から救わなければならない。(92ページ)
著者の加藤喜之氏は、立教大学文学部キリスト教学科の教授である。その以前は、日本の福音派の大学である東京基督教大学神学部で准教授を務められていた。米国の福音派教会で過ごした期間はあるというものの、現在の本人の信仰的立場について本書に記載はない。
しかし、上述の定義は、恐らくは著者自身からは距離をもって記されているように思える。いずれにしても、米国の福音派はキリスト教再建主義などによって多少のふくらみは見せたものの、基本的にはこの定義の教義において広がってきたのではないかと、この書からは読み取れる。
本書の本文は、ジョン・グレサム・メイチェン氏と分離主義や、チャールズ・フラー氏とラジオ伝道を黎明(れいめい)としつつ、大衆伝道者のビリー・グラハム氏の登場による隆盛が、やはり際立って描かれている。彼による影響は、本書のほぼ最後部まで何らかの形で通底している。
大統領と福音派との関わりも、やはりグラハム氏を端緒としている。それは、第34代大統領であるドワイト・アイゼンハワー氏(共和党)との1950年代の親交から始まっている。それが、アイゼンハワー政権で副大統領を務めていたリチャード・ニクソン氏(共和党)の大統領選へと続く。
しかし、グラハム氏はここで2つの挫折を経験している。一つは、1960年の大統領選でニクソン氏が、カトリック信者であるジョン・F・ケネディー氏(民主党)に敗北したこと。もう一つは、その後の大統領選で勝利したニクソン氏が、ウォーターゲート事件で失脚したことである。
米国の大統領は、ほとんどが自民党という一つの政党から選ばれている日本の首相と違い、共和党と民主党からほぼ交互に選ばれている。アイゼンハワー氏以後、一方の政党から3人が続けて大統領になったことはない。ニクソン氏の辞任によって就任したジェラルド・フォード氏(共和党)の後に大統領になったのは、民主党のジミー・カーター氏であった。
それまでは、福音派が共和党の大統領にアプローチする形だったが、カーター氏は自身が南部バプテスト出身の福音派であった。「カーターの登場により、福音派は全米の表舞台に躍り出た。これは、グラハムの蒔(まい)た種が実を結んだ形」であると著者は言う。
しかし、カーター氏は大統領としては成功せず、一期でホワイトハウスを去った。神学的な差異によって、福音派からも距離を置かれるようになったという。民主党の大統領と福音派の距離は、本書の後半でも感じた。
このころに登場したのが、福音派の作家であるハル・リンゼイ氏である。終末世界を描いた『今は亡き大いなる地球』が全米でベストセラーとなり、「携挙」「ハルマゲドン」といった言葉が流布するようになる。本書はこのあたりから、内容が専門的に多岐に及ぶものになっていき、前述したように、私のキャパシティーをはるかに超える、数多くの人名が登場するようになる。
以後、ロナルド・レーガン政権の8年間と、ジョージ・H・W・ブッシュ(父)政権の4年間(いずれも共和党)、福音派によるロビー活動は強くなり、人工中絶反対のキャンペーンが行われる。また、福音派の中にはテレビ伝道のために放送局を持つところも出てくるようになり、ペンテコステ運動が隆盛になり、繁栄の神学が提唱されるようになった。
1990年代にビル・クリントン政権(民主党)になると、福音派のロビー活動は沈静化してくる。この時代は、全米各地に福音派のメガチャーチが建設されるようになる。しかし、2001年にジョージ・W・ブッシュ(子)政権(共和党)が誕生すると、再び福音派と政権の交流が活発化するようになる。
米同時多発テロ事件(9・11事件)をきっかけとするイラク戦争にあたっては、南部バプテスト連盟倫理宗教自由委員会のリチャード・ランド委員長が、ブッシュ氏に対して「正戦論」を説いた。メガチャーチの牧師であるティム・ラヘイ氏によるハルマゲドンを描いた小説『レフトビハインド』が、ベストセラーになったのもこの時代である。
2009~17年のバラク・オバマ政権(民主党)を経て、ドナルド・トランプ第1次政権(共和党)になると、福音派と急進派ユダヤ人が、トランプ氏を後押しするようになる。米国の在イスラエル大使館のエルサレム移転(国際的にはエルサレムはイスラエルの首都と認められておらず、大使館移転はパレスチナに対しては冒瀆〔ぼうとく〕となる)を福音派は歓迎した。彼らの終末論では、エルサレムが首都となり、神殿が再建され、そこにキリストが再臨することが待望されているからである。
著者が本書を通して主張したいことは、このような終末論が、神の摂理によってではなく、世俗の力によって動かされているように見えるということであろう。
以上のように本書は、歴代の大統領を中心とした米国の政権に対して、さまざまな人間がどのような思惑を持ち、どのように動いたかということを分析した書である。福音派に対して、好意的か、客観的か、批判的かのいずれかと問われれば、私は「客観的な捉え方で書いている」と答える。しかし、読者によっては「批判的な捉え方で書いている」と感じる人もいるかもしれない。
最後になるが、グラハム氏は、人種差別に対する風潮がどのような時代にあっても、自身の行った大衆伝道集会において、黒人と白人の席を分けることを許さなかったことを、本書で知った。それは、現代的な人権感覚を持っている人であれば、福音派に対する立場は別にして評価する点であろう。
■ 加藤喜之著『福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会』(中央公論新社 / 中公新書、2025年9月)
◇