藤崎裕之
-
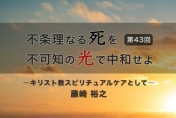
危機感にあふれた時代に黙示録的な解毒(その2)
ダメダメ人間であっても向上心というものがある。裏返せば、このまま死んだらキリストの審査でボロボロにされるという恐怖もあったりする。点数稼ぎもしなきゃならないからまだまだ死ねない。誰もが似たような感覚を持っているのではないだろうか。
-
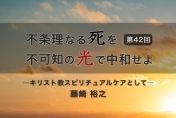
危機感にあふれた時代に黙示録的な解毒(その1)
今回はヨハネの黙示録でも取り上げてみようと思ったのであるが、どうも真剣に目を通す気にならないので、とりあえず20章を開いてみた。この書物は書き出しの1章からして、かなりダラダラしているように思う。
-
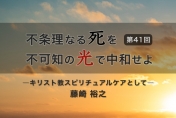
望んでいるようには死んでもらえない(その3)
正直なところ、イエスの言葉は時に難解過ぎるのである。イエスは誰に対しても「わたしに従いなさい」と言われるのであろうか。多分、そうであろう。では、いつから従えばよいのか、と問われれば、「今」からというしかない。
-
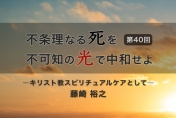
望んでいるようには死んでもらえない(その2)
父が97歳で死んでから半月以上になったが、まだ私の心はモヤモヤしている。その大半は、十分なことをしてやれなかったという後悔である。「十分なことしてやれなかった」というのは、父の信仰に同伴することができなかったという意味である。
-
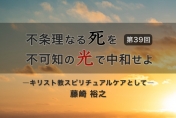
望んでいるようには死んでもらえない(その1)
人はこちらが望んでいるようにはなかなか死んではくれない。と書けば物騒な話ではあるが、要するに、美しいと思う死に出会うことなど、そう滅多にはないということである。キリストを信じているなら、それにふさわしい死に方というものはあるのだろうが。
-
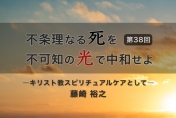
悪霊が悪霊を追い出す?(その3)
イエスは口がきけない人から悪霊を追い出した。毎度おなじみのことだが、助けられた人にとってはおなじみのことではない。この点が大事なのだ。他でもないこの「私」が助けられたのだ。
-
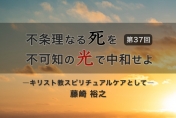
悪霊が悪霊を追い出す?(その2)
口から出るもので一番始末に悪いのが言葉であるが、その言葉の中でも一番悪いのが褒め殺しではないかと思う。褒め殺されていると分かればよいが、人間は何でも都合良く解釈するものだから、私に限って褒め殺しされることはないと思っているのかもしれない。
-
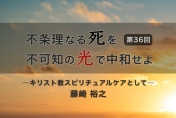
悪霊が悪霊を追い出す?(その1)
悪しき者は天使の顔で近づいてくる。なるほどと思う。しかし、悪しき者はどう見ても悪しき顔をしているのであるが、そんな悪しき者がもたらす「悪しきもの」にいつのまにか依存してしまうのはよくある話である。
-
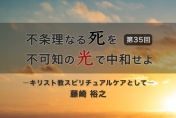
そもそも預言は聞かれたのか(その3)
今回はエレミヤについて少しは悩もうかとも思ったが、他者のことで悩むより、自分のことはどうなっているのかと、そっちの方が深刻になってきた。どうも冬というのは厄介だ、実に気が滅入(めい)る、と今年もそう思うわけである。
-
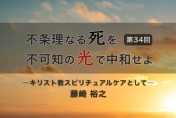
そもそも預言は聞かれたのか(その2)
エレミヤを話題にしているが、エレミヤ書を一意に読み解くつもりはない。大体が預言書というのはややこしいのだ。一通り読み解いたことがあるが、正直同じような内容の繰り返しである。
-
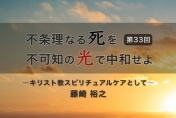
そもそも預言は聞かれたのか(その1)
エルサレムには、いろいろなものがあるらしい。行ったことがないので、書物やネットで知るしかないのではあるが。一番興味があるのは聖墳墓教会の「支店」である。一般的には「園の墓」といわれている場所で、エルサレムの城壁の外に位置しているらしい。
-
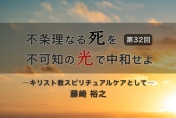
生ける者と死ねる者への裁き(その3)―生死を決めるのは神―
下げたくない頭も、折りたくない膝も、尽くしたくない手も、結果としてイエスにひれ伏すなら、それもありだというのが、聖書の教えるところであろう。人間はいくらでも「ふり」をすることはできる。
-
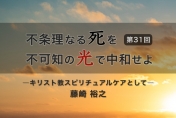
生ける者と死ねる者への裁き(その2)―マルコ5章の隠されたテーマ―
5歳くらいの時に脳炎を患ったらしいのだが、何となく記憶はあるが、深刻さは覚えていない。風疹(ふうしん)脳炎になり、もうちょっとで天使になりそうだったらしく、母親がオンオンと泣いていたと後から知った。
-
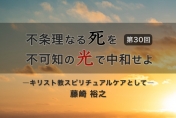
生ける者と死ねる者への裁き(その1)―ヤイロの娘を巡って―
自分は本当に生きているのか、それとも死んでいるのか。模範的な回答をするとしたら、人間誰しもが、キリストの再臨の時にこそ、その人の「生き死に」がはっきりするということなのかもしれない。
-
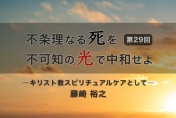
おこぼれは大事だ(その2)
イエスがわれわれに解き明かしているのは、人間の内側にある邪念が人間を汚す、つまりわれわれは安易に言い訳をできないということである。イエスの実際に行われた奇跡や癒やしなどは、現実的、物質的な文字通りのものである。
-
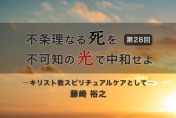
おこぼれは大事だ(その1)
イエスは悪霊の支配者ではないが、悪霊などはいとも簡単にどうにでもできる。と極端な言い方はしないほうがよいのかもしれない。もちろんイエスに可能なのは、悪霊を人間から押し出すことであって、悪霊を人間に憑依(ひょうい)させることではない。
-
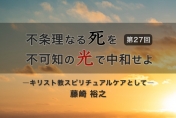
そりゃないでしょう的なバベル譚(その3)
神の前での「へりくだり」というのは難しい。へりくだるふりをするのも実に難しいのである。なぜかといえば、人間は本当の意味でへりくだった人に出会っていないからだ。尊敬心によって丁寧な扱いを受けるということは、しばしばあるだろう。
-
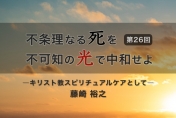
そりゃないでしょう的なバベル譚(その2)
名を高める。そうである。名を高めるためにバベルの人々は頑張ったのだ。どんな小さなコミュニティーといえども、その中で名を高めことには意義がある。とはいえ、名を高めるというのは実のところ戦略的な事柄であって、けして成長的な何かではない。
-
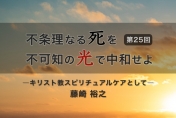
そりゃないでしょう的なバベル譚(その1)
「神意」を読み解くというのは、人間の日常行動でもある。だから「神意」を計るために占いが行われたり――キリスト教はそれを禁じてはいるが――、またこのようなことをすれば神が喜ぶに違いないと考えたりする。
-
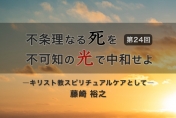
福音は力である?(その3)
パウロはダマスコ途上で復活のキリストに出会い、アナニアを通してキリストへと目を開かれるのであるが、使徒言行録では「わたしが選んだ器である」というイエスの言葉をもってパウロについて語られている。
人気記事ランキング
-

英米の聖書販売部数、過去数十年で最高を記録 6年で倍増の勢い
-

ワールドミッションレポート(1月31日):チベット イエスに出会ったチベット仏教僧―光の使者になる④
-

米ワシントンの教会、礼拝出席者が7年で20倍に 信仰に立ち返る若年・中堅世代たち
-

ヨハネの黙示録(12)天に一つの開いた門 岡田昌弘
-

AIに心を持たせることは可能なのか クリスチャンの東京科学大学名誉教授が解説
-

UFOと終末預言がテーマ クリスチャン映画「未確認」「収穫の終わり」が日本語字幕化
-

篠原元のミニコラム・聖書をもっと!深く!!(264)聖書と考える「パンチドランク・ウーマン」
-

ワールドミッションレポート(2月3日):ヨルダン 安定の陰で忍び寄る不寛容、揺らぐ共存
-

衆院選で外国人敵視拡大に懸念、外キ協など11団体が共同声明「排外主義の扇動に反対」
-

聖書原語への招き―霊に燃え、主に仕えるために(1)霊に燃える 白畑司
-

米ワシントンの教会、礼拝出席者が7年で20倍に 信仰に立ち返る若年・中堅世代たち
-

ムラリー主教、第106代カンタベリー大主教に正式就任 1400年の歴史で初の女性
-

AIに心を持たせることは可能なのか クリスチャンの東京科学大学名誉教授が解説
-

UFOと終末預言がテーマ クリスチャン映画「未確認」「収穫の終わり」が日本語字幕化
-

ワールドミッションレポート(1月31日):チベット イエスに出会ったチベット仏教僧―光の使者になる④
-

韓国の合同捜査本部、「新天地」の本部などを家宅捜索 政界との癒着疑惑で
-

衆院選で外国人敵視拡大に懸念、外キ協など11団体が共同声明「排外主義の扇動に反対」
-

無料オンライン講座「キリストの基礎知識コース」第11期受講者募集 2月14日開講
-

主にある目的思考的生き方 万代栄嗣
-

ワールドミッションレポート(2月2日):チベット イエスに出会ったチベット仏教僧―光の使者になる⑤
-

米ワシントンの教会、礼拝出席者が7年で20倍に 信仰に立ち返る若年・中堅世代たち
-

AIに心を持たせることは可能なのか クリスチャンの東京科学大学名誉教授が解説
-

ワールドミッションレポート(1月31日):チベット イエスに出会ったチベット仏教僧―光の使者になる④
-

UFOと終末預言がテーマ クリスチャン映画「未確認」「収穫の終わり」が日本語字幕化
-

ムラリー主教、第106代カンタベリー大主教に正式就任 1400年の歴史で初の女性
-

衆院選で外国人敵視拡大に懸念、外キ協など11団体が共同声明「排外主義の扇動に反対」
-

韓国の合同捜査本部、「新天地」の本部などを家宅捜索 政界との癒着疑惑で
-

無料オンライン講座「キリストの基礎知識コース」第11期受講者募集 2月14日開講
-

主にある目的思考的生き方 万代栄嗣
-

ワールドミッションレポート(2月2日):チベット イエスに出会ったチベット仏教僧―光の使者になる⑤
















