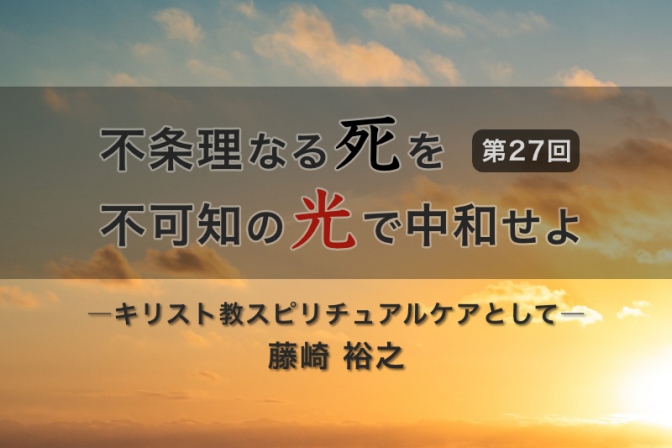不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(27)
※ 前回「そりゃないでしょう的なバベル譚(その2)」から続く。
やってられません!
神の前での「へりくだり」というのは難しい。へりくだるふりをするのも実に難しいのである。なぜかといえば、人間は本当の意味でへりくだった人に出会っていないからだ。尊敬心によって丁寧な扱いを受けるということは、しばしばあるだろう。でも、それは人間同士のこと。神にへりくだるというのは、いや、そのへりくだりを神が認めてくれるというのは、まさに神業なのだ。人間には判断がつかないのだ。だから当面のところ、その答えはわれわれには与えられていないということを承知するのが大事である。いや、そう思わないと生きていられないのだ。われわれは自分自身のへりくだりを何としても神に見ていただきたいと願うだろうか。確かにそういう場合もあるだろう。わがへりくだりに顔を向けてくれる神であってほしいと思うこともあるだろう。
さらに、こういうこともいえるかもしれない。人間社会を生きていくコツのようなものだ。つまり、へりくだっているふりをしないと生きていけない社会が存在しているのだ。それが人間に対するものでも、神に対するものでも同じだ。へりくだるとか、頭(こうべ)を垂れるというのは、日常的なことであるから適当にやり過ごすこともできる。むしろ、適当にやり過ごせない人は大変に苦労するものである。そこに心がこもっていようが、なかろうが、われわれのへりくだりが一応のところで受け入れられないなら、それはもう「やってられません!」ということになる。実際にどのように評価されるかは別問題だ。へりくだりの姿勢を「いいよ、いいよ、それでいいんだ」と認めてほしいのだ。
大丈夫だったのか
バベルの人々も、まさか本当に神から「へりくだり」について判定されるなどと思いもしなかったのではないか。実際にダメ出しされたから、この話には価値があるのだが。いつの時代も神は仮定にすぎない。どんなに優れた宗教家であっても、伝説を残すほどの信仰者であっても、神は仮定にすぎない。仮定にすぎないから「信じていない」と言っているのではない。神がいかなる方であるのか、人間は全てを知ることができないから、どんな人間であっても神は仮定にとどまるのだ。むしろ、その方が良いに決まっている。神がいかなる方であるのか知り得るとしたら、恐らくその人はその神をまねて良からぬことを始めるに違いないのだ。実際に神を少しも分かっていないのに、神を理解していると錯覚した御仁が、神に成り代わって悪態をさらすということがしばしばあるではないか。
バベルの人々にとって、神の存在は了解事項であっても、それでも神はある種の仮定にとどまっている。何となくではあろうが、彼らは神に対する意気込みを示そうとか、神のために玉座を用意しようとか、適当なお題目を並べながら、一致協力して高い塔を造っていたのである。それがバベル塔の本質なのだ。実際のところ、それぞれの本音が何であろうと、とにかくかりそめにでも一致して何かを成し遂げるということ、それを良しと考えるのもまた人間である。それはそれで美しい。一生懸命だ。そうでなければ立派で美しい宗教施設などこの世には残りやしないのだ。
「これで神に喜んでいただける」と本気で考えてしまうから「痛い目」に遭うのだ。「とにかく神のために!」という合い言葉で事を成し遂げる。強制されてむち打たれながら成し遂げようが、バベルの人々のように一致団結して成し遂げようが、同じことなのかもしれない。というのも、人間がその能力の最高地点を駆使して建て上げたものも、実は役立たずであったりするからである。必要をとっくに超えているにもかかわらず、より高く、より大きく、と終わることのない欲望の中で人間の能力がフル稼働されていくのだ。
何千年も後に「これってすごいね。どうやって造ったのだろう」と驚かれる代表的なものとして、エジプトのピラミットや日本の大古墳があるが、墓としてはどう考えても大き過ぎるではないか。当時生きていた人々にとっては、胃袋を何一つ満たさないものである。そこから何か、人々の生活に必要なものが再生産されていくわけではない。幾らかの人々の自尊心を満たしたとしても、それでお腹はいっぱいにはならないのだ。どえらい建物も、必要を超えているなら無駄なのだ。
収穫する量の何倍もの量が入る蔵を建てて何の意味があるだろうか。蔵を建てる前に土地を耕し、種をまき、世話をしないといけない。巨大な玉座を建てる前に、その玉座の工事を行う人々の食事はどうなっていたのか気になる。「おいおい、そんな工事やって大丈夫なのか。食料生産は間に合っていたのか。そんな社会はすぐに崩壊するんじゃないか」と想像する方が、ずっと健全なのではないかと思うのである。
神のためなら無理できる?
ある学説によると、食料生産の余剰があったから巨大建築をできた!ということになっているが、本当にそうだろうか。そもそも無理して何かを成し遂げることに意味を感じているわけで、そうでなかったら玉座の意味がない。それこそ「余裕があるからあなたのために!」ということであれば、へりくだりにはならないではないか。わが身をすり減らしてこそ、へりくだりだと思うのが、われわれ地上民の発想なのだ。
オランダやイングランドのピューリタンによれば、選ばれし信仰者は聖霊の働きによって抑えがたい善意から本物の善行を成し遂げることができるという。筆者はピューリタンの末裔(まつえい)ではあるが、それについては全く理解し難い。せいぜい人目を気にしながら「へりくだり」を装い、これではバレバレだと思いつつも、まあ一致団結の端っこでジタバタしているくらいなのだ。
「われわれが全地に散らばらないようにしよう」とお題目を掲げつつ頑張っているバベルの人々の情熱を認めようではないか。頑張ったのだ。「高く、高く! 神のためにより高く、美しく!」 それが彼らのへりくだりだ。不遜だとか、おごり高ぶりだとか、勝手なことを言うくらいなら、少しは地上民として彼らに共感する方を選ぶべきなのかもしれない。
小さい、まことに小さい
しかし聖書によると、神は彼らが建てた町と塔を見るために「降ってこられた」。そう、残念ながら、天からは高い塔も見えなかったのだ。そういうものだ。人間とはそういうものでしかない。神への情念であろうが、神への不遜とおごり高ぶりであろうとも、人間が一致団結して成し遂げたとしても、やはりそれは天から見ればあまりにも小さい。天にいる神には見えないのだ。何と悲しいことであろうか。何と惨めなことであろうか。その事実が、こんな昔から当たり前のように認識されていたのだ。人間が成し遂げることは全てが神の前には小さ過ぎるのだ。まさに「そりゃないでしょう」的な何かである。あとは知られているように、バベルの人々は互いに言葉が通じなくされ、建設は中止し、そして彼らは全地に散らされていっただけだ。
徒労に終わった大建築であったが、後世の人々は「すごい」ものだと賞賛してくれるだろう。昔の人間はすごいものを造ったと感心してくれるだろう。しかし、事実は違う。人間は散り散りバラバラになっただけである。文明も技術もその結果も、それは後世には残ったかもしれないが、しかし人間は散り散りバラバラになっただけ。以降、部族が部族に、民族が民族に、国が国に敵対して戦争を繰り返してきただけではないか。われわれの時代はどうなっているだろうか。われわれがなしていることは神の前に小さいと思えるだろうか。あるいはにせの「へりくだり」によって、「高く、高く、神へと高く」を繰り返しているのだろうか。
われわれは自分たちの一致、努力、勤勉によって成し遂げたことが、「そりゃないでしょう」的に崩れ去る経験を繰り返している。どこかに自分たちに落ち度があったのではないかと反省もする。でも、考えるべきは、われわれに本当の意味での神への「へりくだり」があったかどうかである。神が降ってこなければ見えないような小さな、まことに小さな成果を「神の栄光のために」と思い上がり、自己讃美していないか点検すべきである。神はへりくだった魂を愛されるというのは本当のことではないかと思うのだ。散り散りバラバラにされた人間が、小さいままで生きていけるとしたら、それがキリストの平和ではないのだろうか。(終わり)
◇