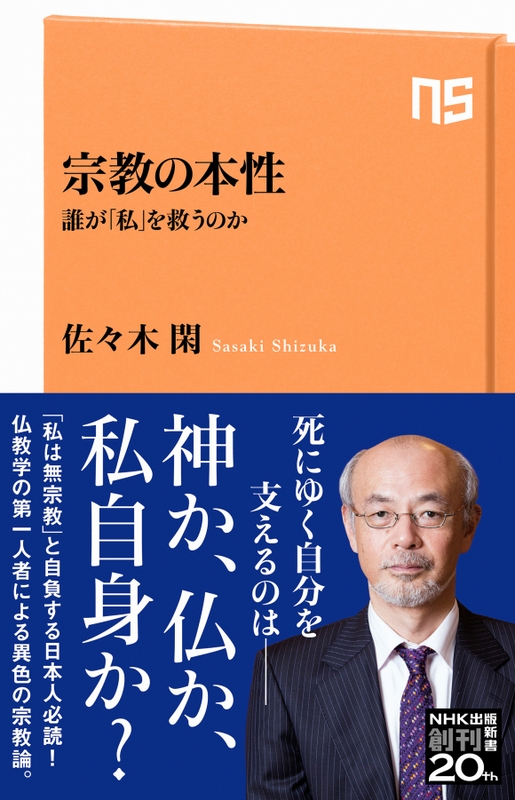本書は、「宗教」とされる団体、またはその関連施設に関わるすべての人が一度は読むべき一冊である。往々にして「宗教家」(特定宗教を社会に浸透させることを生業とする人々)は、己の信奉する「宗教的世界観」のみを「真理」として受け止めてしまう傾向が強い。それは端的に言うなら、「聖典にこう書いてある」とか、「○○師の教えによると・・・」という言い回しで、この世界を色付けしようとする行為である。だが、そうした聖典や教えは、この世のすべての人々の間にアプリオリ(自明)に存在しているものではない。その証拠に「全世界共通の宗教」というものは存在しない。
「世界三大宗教」と称されて久しいキリスト教、仏教、イスラム教ですら、各宗教内で統一がとれているわけではない。近親憎悪とまではいかないが、各宗派内で争いは絶えないし、互いに相手に対し「異端」というレッテルを貼り、愛と解放、自由と協調を説く教えであるにもかかわらず、その内部には大きな温度差が生じていることが往々にしてある。
そんな諸宗教の違いをどう捉えたらいいのか。特に他宗教とどう向き合っていけばいいのか。本書は、宗教家がなかなか外に向かって発することのできないネガティブな心情を見事にすくい上げ、そして一つの「道(考え方)」を提示してくれている。
著者の佐々木閑(しずか)氏は、花園大学文学部仏教学科の教授である。すると、ゴリゴリの仏教専門家のようなイメージを与えるが、実は京都大学工学部で理系の学びも修めている。だからこそ、本書でも取り上げられている科学と宗教の「相克」を的確に捉えることができ、さらに一歩進むためのロジックを皆が納得できる形で提示できるのだろう。
本書はNHK文化センターでの講演が基調となっているため、章立てもそれに倣い6講立てとなっている。冒頭で著者が講義の構成を説明してくれているので大変分かりやすい。第1講から第3講までは、「客観的な視点」から見た宗教の位置付けを語っている。参考図書として、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』を用いることで、誰が読んでも理解できる叙述を心掛けている。
一方、第4講から第6講にかけては、「主観的な視点」から見た宗教について語っている。ここは当然、佐々木氏の「仏教観」が前面に出てくるため、仏教ビギナーにとっては「言っていることは分かるけど、ちょっとつかみづらい」と思うかもしれない。しかしこの後半のポイントは、決して「仏教は素晴らしいでしょ」というだけではない。前半の客観的な視点で見た宗教(この段階では仏教のみならず、キリスト教やイスラム教などの諸宗教も含まれる)を踏まえるなら、各々が信じる宗教に置き換えてここを読むことも可能である。
例えば私など、「仏教と(私の信じている)キリスト教は、こんな点が違うのか」と、その陰影がよく分かった。これは自らの信仰を客観的に眺めるためにとても必要な視点である。しかし、牧師という立場上、普段はどうしても近視眼的にキリスト教を捉えてしまうため、俯瞰(ふかん)的な視点を得ることは難しい。つまり、「かゆいところは分かっているけど、かくことができない」という状態から自力では抜け出せないのである。本書はまさにその解決のポイントをしっかりと提示してくれている。
宗教を客観的・主観的視点で捉える考え方は、本書の冒頭で「薬」を例に挙げて説明されている。客観的とは「学術的なアプローチ」ということであり、例えば薬の成分や効用などを列挙することになる。これは「学者の目から見た宗教」に他ならない、と佐々木氏は語る。一方、主観的になるとまったく違った様相を呈する。「その薬に私のすべてがかかっていて、生き延びる唯一の道」となる。ここから敷衍(ふえん)し、宗教も「こういうものだ」と理解することは誰でもできるが、死を目前にして、何かにすがらないと生きられない状況に追い込まれると、それまでとはまったく違った感覚で宗教を捉えるようになるのである。
この両側面が各々の異なる指標となり、私たちの信じる宗教を新たな視点で評することができる。自分たちが信じている「宗教」に、今までとは異なる新鮮な立場で遭遇することができる、と言ってもいいだろう。少なくともキリスト信者である私は、「キリスト教」に対し、本書を通して新しい切り口で向き合えることを知ったし、より一層自らのアイデンティティーを深く愛することができるようになった。
客観的と主観的。多くの日本人は前者の立場から宗教について語られることを好む。「信じるほどではないが、一体どんな教えなのか気になる」というのは、一般的な日本人の宗教への向き合い方だろう。しかし、時として後者が勝るときもある。それは、この地に生まれてきた私たちが絶対に避けては通れない事柄、すなわち「死」と現実的に向き合うときである。著者は、ハラリの言葉などを用いて「宗教」という概念を、現存するイデオロギーもろもろにまで拡大させる。しかし論が深められていくと、「現世でいかに生きるか」を説く宗教的なものは数多くあれど、「死」と向き合うことに耐えられる宗教は決して多くないことが指摘される。
人にとって、自分が死ぬということ以上に重大な問題はありません。理に叶(かな)っているかどうかは二の次で、一番重要なのは、その人にとって説得力ある言葉かどうかです。その話を聞いた本人が信じて、本人が救われるのであれば、それはその人にとって、まぎれもない真実だということです。(142ページ)
そして、それから自身の宗教体験を語り始める第4講の最後に、佐々木氏は次の一文を添えている。
もしこの講義を、別の宗教を信奉している人が語っているとするなら、ここから先は、その人の宗教体験が示されることになるでしょう。(154ページ)
私はこの抑制の効いた一文に、完全にノックアウトされてしまった。つまり、佐々木氏は仏教を取り上げながらも、最終的に他宗教をも生かす道を提示しているのである。心憎い配慮であるし、これこそが「宗教」というものの本性として、多くの読者が首肯できる着地点だといえるであろう。
単なる「仏教宣伝の書」と見誤ることなかれ。私たちキリスト信者は、佐々木氏が第5講、第6講で語っている内容を、今度は私たちの信仰から語り直すことを後押しされているのである。本書は、キリスト教会の牧師であるならきっと大きなチャレンジを受けることになるだろう。ぜひ本書に向き合ってもらいたい。
■ 佐々木閑著『宗教の本性 誰が「私」を救うのか』(NHK出版、2021年6月)
◇