F 世界宣教
フィリピン戦争の最中の1900年に、教会史上で最大の宣教大会がニューヨークで開かれ、参加者は10万人を数え、外国宣教の熱が高まっていた。大統領自らが世界宣教に関して説教したりした。
当時の終末に関する聖書主義的な立場は「ポスト・ミレニアル・リターン・オブ・クライスト」であった。すなわち人類の文化が進み、やがて繁栄と平和の時代が来て頂点に達する。その時から千年間の王国が開始される。人は長寿を楽しみ、理想の世界に暮らす。その終末にイエスが再臨され、ついで新天・新地が現出する、というものである。
この「ポスト・ ミレ」の考え方は連続的な終末観で、20世紀初頭のはなはだ楽観的な歴 史観、絶え間なく進歩する人間社会という見方とセットになっていた。
現在福音派の多くが奉じている「プレ・ミレニアル・リターン・オブ・クライスト」とは、これとは反対の歴史理解を持っており、世界は悪化の一途を辿り、最悪の状態に至る。その時キリストの再臨があり、その後で千年の王国が現出する。王国の終わりに世界の裁きの時があり、ついで新天・新地が現出するというものであり、非連続が特徴である。なお千年王国時代は地上で起こるものであり、文化命令の成就の時でもある。
ポスト・ミレの思想は第1次大戦を期に減少し、ヒロシマ以後、これを唱える者はいなくなったが、当然である。
現在の教会時代がすなわち千年王国時代であると考える「ア・ミレニアル・リターン・オブ・クライスト」もある。ア・ミレの思想では、文化命令の成就する場は教会時代で現在の世界を含む。これも近・現代に対するやや楽観的な見方の痕跡を持っているように見える。福音派の中の少数がこの立場を取る。
ボシュは、彼の伝道学の著書で述べているが、20世紀初頭には「米国は神の特別なご計画のうちにある国家」だとの信念が強烈であった。「マサチューセッツ州のある地方では、すでに明白に千年王国の始まりの予兆が見られる・・・」と報道している新聞もあった、という。
20世紀初めの米国のプロテスタント教会の宣教熱は、この「千年王国の予兆を含む素晴らしい米国文化」を外国に伝える、ということも含んでいた。こうして米国的なライフスタイルを教えることが「福音それ自体」を教えるということとセットになっていた。(Bosch, Transforming Mission, Paradigm Shifts in Theology of Missions, 0rbis)
日本にもこの時期、ミッション・スクールが多く設立された。これらミッション・スクールは日本社会に二つのことを教えようとした。一つは福音を教えることであり、もう一つは米国的な価値観やライフスタイルを教えるのである。
ミッション・スクールの生徒は「バタ臭い」とも「アカ抜けしている」とも言われたが、これはミッション・スクール設立の目的の2番目の影響である。パール・バックは長老派の宣教師であったが、「中国に米国的な生活様式を教える」のが宣教活動のうちの大きな眼目であったと言っている。
岩波文庫版の『フランクリン自伝』には、フランクリンがシアトルでインディアンの部族の長老たちが泥酔しているのを見たときのことが出ている。フランクリンはそのありさまを見て「この人々を滅ぼして、新しい国を作ることがわれわれに与えられた神からの使命であり・・・」と言っている。
民主主義の父とも呼ばれているフランクリンの、当時の米国社会の先住民に対する意識をいみじくも表現している。(なお「滅ぼし」が英語の原文でどんな字を使っているかは調べていない。)
<進歩の概念>
さて、マニフェスト・デスティニーの根底にあるものは進歩の概念であり、次のような行動の原則を含むといえる。a. 人類は全て進歩の道を歩んでいる。b. 人類の進歩の道筋は単一であり、複数のルートはない。c. 全ての民族の文化は、その単一の道程のどこかに位置している。d. プロテスタント・キリスト教文化は、最高の文化である。e. 「進んで」いる者は「遅れて」いる者を指導する。f. その指導は、多少は荒っぽいことがあっても、やむを得ない。g. 乱暴な指導もしまいには感謝される。(h. 指導を理解せず、毒矢などをもって対抗する者は殺してもいい。 むしろどんどん殺した方が人類全体のためには有益である。)
カリフォルニアではインディアン狩りの政策が取られ、インディアンを殺して頭の皮を持って行けば報奨金が与えられた。パサデナのラルフ・ウィンター博士によれば、彼の幼少時に、近所にそれで生活していたことのある老人がまだ生きていたということである。
この「インディアン狩り報奨金」の問題は、全米的スケールでも行われていたようである。戦後にシアトルで行われたインディアン首長大会では、そのことが取り上げられた。(My Brother’s Keeper : The Indian in white America, ed by Edgar Kahn & David Hearn, New American Library 1970)
米国流の自由と平等と人格の尊厳の概念には、実はその基底に上に挙げたような前提がある。この差別的な前提概念は欧州の伝統であり、別に米国の発明ではない。ただ欧州ではこれは適当に隠蔽(いんぺい)されており、むき付けに表現されることは少なかったようである。欧州では人種問題というものはインドやアルジェリアなどの遠い植民地でのはるかな出来事であった。
ところが米国は国内の発展のために奴隷を使用し、それなしには南部の経済は考えられなかった。また、先住民族がそこここに住んでおり、これは追い出し、土地を奪い、追放し、その途中で反抗すると殺りくする、ということを繰り返した。やがてその追放した先の土地もまた欲しくなり「追殺りく」というようなことを繰り返してきたのである。
米国の文化は、そういうことが身近に起こっているのを「無視する」「見なかったことにする」などのことを数百年続けてきた。その結果、米国ではまことに偽善的な文化が成立した。建前と実際の違いの文化である。
米国人はフランクで、現実的である、世界で最も人権について良心的な国である、などと大真面目で主張する国となった。その心理はあまりにも複雑である。表面は単純・素朴・陽気を演じる。正直な日本人がだまされるのも当たり前である!
カーターが大統領であったとき、南アのアパルトヘイトについて抗議したところ、南ア大統領のデクレルクは答えて「米国のピューリタンは、インディアンを皆殺しにしたので、今問題はないが、オランダ改革派教会は黒人を殺さず分離しながら共存してきた。それ故の問題である」と言ったそうである。どちらも同罪なのだが。
欧州とは違い、米国では奴隷制を整備し、正規の商品として認め、奴隷の取引と流通のための法制度を整備した。であるから米国では、奴隷商人はヤミ商人ではなく、法律に規定された正規の職業だった。
<宣教学とマニフェスト・デスティニー>
なおマニフェスト・デスティニーと世界宣教の関係を論じたものは、米国の宣教学者のものの中にはないようである。ボシュとフェルキュイルだけがこれについて短く述べているだけである。それぞれ南ア人とオランダ人であるが、米国人はこの重要な主題について沈黙しているようである。
実はこの問題を論じることは福音信仰やまた改革主義信仰と呼ばれているものの中心近くにシビル・レリジョンが存在することを認めることにつながるので、そのために論述を避けているのだろうか。
それとも、単にそのことに気が付いていないだけだろうか。気が付いてないとすれば、何百年の西欧的キリスト教信仰のタブー伝統にまさしくのっとっているのである。
シビル・レリジョンとは、市民信仰とでも訳すべきか、その時の社会を支配するイデオロギーやエートスと合致していて、そのために広く支持されている単純な宗教思想の単位のことである。
民族性や、社会の利害に合致するので支持されているのであるが、聖書とは直接関係がないものをいう言葉である。よく米国人が言う「われわれはクリスチャンである。だから資本主義者である。ゆえに共産主義はサタンの教えである・・・」などというのは一つの典型である。
このあたりの解明はアジア、アフリカ、南米のクリスチャンが声を上げる以外にないのであって、こういうものは、こちら側からの視点で初めて見えるものかもしれない。植民地化を極端に恐れ、さまざまな手段を使って独立を保ってきた日本こそ、このような要素を最もよく見抜ける立場にあるのではないか。
(後藤牧人著『日本宣教論』より)
*
【書籍紹介】
後藤牧人著『日本宣教論』 2011年1月25日発行 A5上製・514頁 定価3500円(税抜)
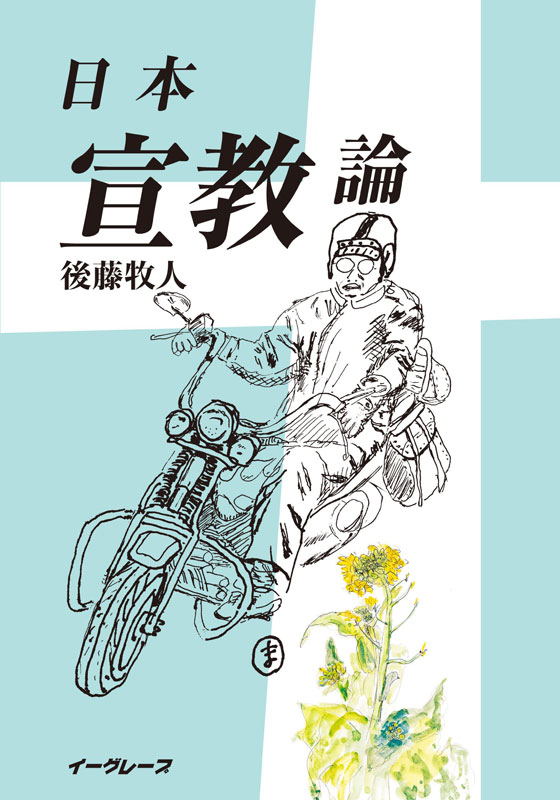
日本の宣教を考えるにあたって、戦争責任、天皇制、神道の三つを避けて通ることはできない。この三つを無視して日本宣教を論じるとすれば、議論は空虚となる。この三つについては定説がある。それによれば、これらの三つは日本の体質そのものであり、この日本的な体質こそが日本宣教の障害を形成している、というものである。そこから、キリスト者はすべからく神道と天皇制に反対し、戦争責任も加えて日本社会に覚醒と悔い改めを促さねばならず、それがあってこそ初めて日本の祝福が始まる、とされている。こうして、キリスト者が上記の三つに関して日本に悔い改めを迫るのは日本宣教の責任の一部であり、宣教の根幹的なメッセージの一部であると考えられている。であるから日本宣教のメッセージはその中に天皇制反対、神道イデオロギー反対の政治的な表現、訴え、デモなどを含むべきである。ざっとそういうものである。果たしてこのような定説は正しいのだろうか。日本宣教について再考するなら、これら三つをあらためて検証する必要があるのではないだろうか。
(後藤牧人著『日本宣教論』はじめにより)
ご注文は、Amazon、または、イーグレープのホームページにて。
◇



























