前回は、分子進化の中立説と深く結び付いている「分子時計」は特殊な条件下で成り立つ性質であり、進化の証拠とは見なされていないことをお話ししました。
今回は、現在の進化学では、突然変異は偶然に支配されているが、自然淘汰(とうた)はランダム(無秩序)な突然変異から生存と繁殖に有利な変異を選び出して進化を引き起こす創造的な力がある、と想定されていることを説明します。
現在、自然淘汰が秩序を造りだすことを説明する理論は存在しませんが、進化学のパラダイムでは自明の前提とされているのです。
【今回のワンポイントメッセージ】
- 自然淘汰には、数百万年もの時間をかければ偶然から秩序を造りだす創造的な力があることを、想像力を発揮して理解すべきである、と木村資生(中立説の提唱者)とリチャード・ドーキンス(進化論の推進者)が唱えている。
形態の進化を説明する理論が存在しない
これまでに説明しましたが、現在の進化学では、DNA(またはタンパク質)分子の進化を扱う中立説と形態の進化を扱う自然淘汰説を結び付けて形態の進化を分子レベルで説明することができません(第36回)。
また、進化学で扱われている数学的理論は、全て確率・統計的な計算であり、厳密な科学理論からほど遠いのです(第37回)。
従って、形態の進化のプロセスを説明する具体的な理論が存在しません。これが、今日もなお進化学における最大の未解決問題なのです。このことは、進化学者アンドレアス・ワグナーが近刊書(2014年)で、次のように述べていることからもうかがえます。
「いかにして新しい表現型(注:新しい形態)が生じるかという謎は、一世紀以上にわたって科学の歩みを遅らせてきた・・・この難題は・・・アルコール脱水素酵素のような最小限のタンパク質(注:517個のアミノ酸配列を持つ)をとってみてさえ、きわめて難しいものである。なぜならアミノ酸をつなぎ合せるやり方が、全宇宙の水素原子数より多いからだ」【文献1[ 47、48ページ]注:筆者】
さらにワグナーは、
「ダーウィンの時代以来ずっと念仏のように繰りかえされてきたランダムな変化をもちだすのは・・・役に立たない。ただ茫然とするほどの確率の低さを考えると、自然淘汰だけでは不十分なのだ」【文献1[48ページ]】
と述べて、宇宙には膨大な可能性の中から必要なものを選び出す能力があるという新しい数学的な原理を提起して、ランダムな突然変異からなぜ形態が進化するのかという難問に答えようとしています。
自然淘汰が秩序を造りだす――「猿のタイプ打ち」の例え
木村資生は、ヒトを作り出すための情報がDNA分子に出現する確率があまりにも小さいことを示して*、「どんなに大きな時間と空間を与えても、偶然だけで生じることは不可能である」と述べています。【文献2[154、155ページ]】
- [*およそ10の6千万乗(1000・・・0と1の後に0が6千万個並ぶ数)分の1にしかならないという計算例を示している]
しかし、ここで木村は、偶然のプロセスに自然淘汰が働けば可能になると唱え、これを猿に無秩序にタイプライターを打たせてシェイクスピアの作品を1ページ分作るという例えで、およそ次のように説明しています(図1)。
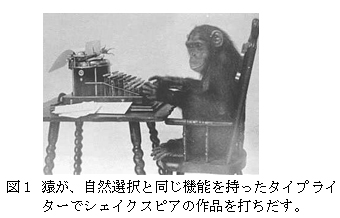
猿がでたらめに打つのであれば、100億年かかっても可能性はない。しかし、猿に一字ずつ打たせ(突然変異に相当)、それが正しい字でなければ消してやり直させ、うまく正しい字が打たれたら次に進む(自然淘汰に相当する)ようにすれば1年もあれば十分である。
木村は、このように自然淘汰には偶然に起きる突然変異の中から、目的とする変異を選び出して生物を進化させる創造的な力があると唱え、
「突然変異自体は一定の方向をもたぬ、いわばでたらめなものであるが、自然淘汰はこれとは正反対で、無秩序から秩序を生む機構であることが、一般にはよく理解されていないのである」【文献2[154ページ]強調:筆者】
と主張しています。
無神論的観点から進化論を広めているリチャ-ド・ドーキンスも、「猿のタイプ打ち」の比喩で自然淘汰の働きを説明し、
「私の仕事の一つは、ダーウィン主義が『偶然』についての理論であるという、根強い神話を破壊することである」
と述べています。【文献3[11ページ]強調:筆者】
「猿のタイプ打ち」の真意
ドーキンスは、猿の代わりにコンピューターで次々と乱雑に文字群を発生させ、目的とする文章の語句に最もよく似たものを選び出す機能を持たせたプログラムを用いて、目的の文章が次第に完成していく様子を記しています。【文献3[87-95ページ]】
ところが、木村もドーキンスも、目的とする文字や語句を選び出す仕組み、すなわち「進化に必要なものだけを選択する」自然淘汰のメカニズムについて何も説明していません。また、それが起きた実例も示していません。
それゆえ、「猿のタイプ打ち」の例えは、多数の偶然の事象が同時に一斉に起こるのを待つよりは、目的とする事象を一つずつ選んで累積していった方がはるかに早く済む、というごく当たり前のことを示しているにすぎません。
自然淘汰を理解するには「長時間に対する想像力」が必要
従って、自然淘汰によって偶然から秩序が生み出されるとは簡単には信じられません。しかしドーキンスは、自然淘汰の働きが信じがたい理由を次のように説明しています。
「われわれは、数秒、数分、数年、もしくはせいぜい数十年で完結する過程を認識するようにできている。ダーウィン主義は、数万年から数千万年もかかって完成するほど緩慢な累積過程についての理論である。だから、・・・われわれが直観的に判断しても、・・・はなはだしく見当違いな結果になってしまう」【文献3[11ページ]】
つまり、タイムスケールの違いが、自然淘汰の理解を妨げていると指摘しているのです。それゆえドーキンスは
「慣れ親しんだタイムスケールの虜(とりこ)から逃れるためには想像力が必要であり、私はその想像力をかきたてるのに一役かうつもりである」【文献3[12ページ]強調:筆者】
と言っています。木村も想像力が必要なことを次のように述べています。
「自然淘汰のもつ創造的な力を理解する上でのもう一つの困難は、われわれの持つ想像力の限界である。物理学では数学的理論の助けを借りて時間的空間的に日常生活の体験の範囲をはるかに超えた世界の現象を論じることができるが、生物進化においては今のところ、そのような段階には達していない」【文献2[156ページ]強調:筆者】
21世紀の現在でも、自然淘汰が秩序を創りだすことを説明する理論は存在しません。自然淘汰には、数千万年の時間スケールで秩序を造りだす創造的な力が存在することが、進化学パラダイムでは自明の前提とされているのです。
【まとめ】
- 現在、主流の進化学パラダイムでは、ランダムに生じる突然変異に、数百万年以上の時間スケールで自然淘汰が働くことによって繁殖に有利な変異が選びだされて進化が起きることが自明の前提とされている。
- つまり、突然変異は偶然に支配されているが、自然淘汰には秩序を造りだす創造的な力があると想定されている。しかし、これを説明する理論は存在しない。
- 理論が存在しないという困難を克服して自然淘汰の創造的な力を理解するためには、想像力を発揮して数百万年以上の時間スケールで自然淘汰が働くことを理解することが必要、と木村とドーキンスが主張している。
【次回】
- 生命現象の根底に存在する「情報」、およびパターン認識理論などの「理論」が、はたして偶然のプロセス(自然淘汰)で作られるか、という問題を考察します。
【文献】
- 1)『進化の謎を数学で解く
』、アンドレアス・ワグナー著、垂水雄二訳、文藝春秋(2015年、英文原著2014年出版)。
- 2)『分子進化の中立説
』、木村資生著、木村資生監訳、向井輝美、日下部真一訳、紀伊国屋書店(1986年、英文原著1983年)。
- 3)『盲目の時計職人
』、リチャード・ドーキンス著、日高敏隆監訳、中嶋康祐、遠藤彰、遠藤知二、疋田務訳、早川書房 (2004年、英文原著1986年)。
◇