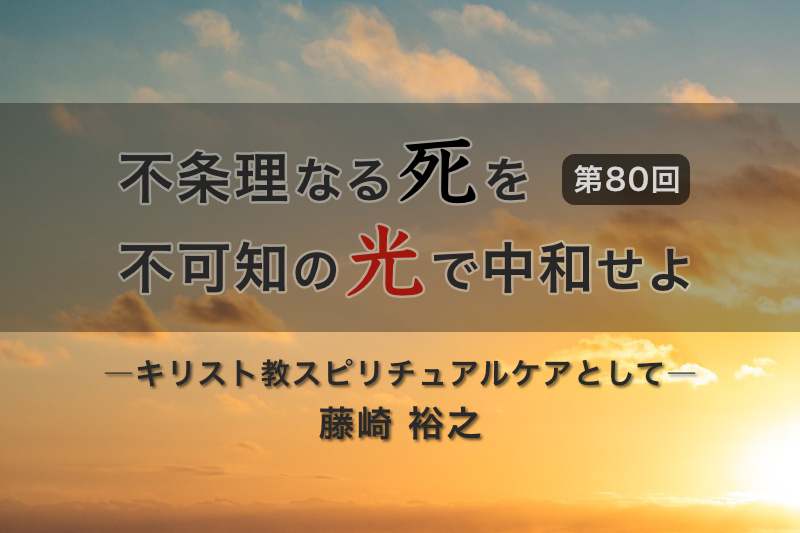
不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(80)
※ 前回「復活はないのか(その1)」から続く。
兵士たちは、祭司長や長老たちから多額の金を受け取ってうその証言をした。「弟子たちが夜中にやって来て、我々の寝ている間に死体を盗んで行った」と。見張り役としてはどうかと思う。自分たちが全く見張り役になっていないということを、証言させたということになる。
遺体を盗まれるということに、どれほどの落ち度があるのかは私には不明であるが、見張っていたはずの遺体を、丸腰の弟子たちに盗まれたわけであるから、兵士としてはめちゃくちゃ不名誉なことだろうと思う。自分たちの不名誉をさらしてもよいと思うくらいに多額のお金であったと想像するべきか、あるいは、お金というものは兵士に名誉を捨てさせるほどの誘惑となったというべきか。
「この話は、今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている」とマタイは証言しているのであるが、マタイが福音書を書いたであろう時期は、この事件の少なくとも40年くらい後のことであるから、随分長い間、イエスの遺体は盗まれたのだと記憶されていたことになる。イエスの復活はなかったのだ、墓が空になって遺体が行方不明になってしまったのは、キリスト教徒たちの「工作」であったのだ、ということにされていたわけである。
マタイの証言がまあまあ確かであるとしたら、とにかくイエスの墓には死後3日目から遺体がなかったということが、ユダヤ人たちの間でも認められていたということになる。これは大スキャンダルではないか。
イエスの墓は空っぽになってしまったのである。私は殺されるが必ず復活すると宣言していた人物は、少なくともその遺体のままで墓に埋葬され続けていたわけではないのだ。故に当時のキリスト教徒たちは、イエスの墓参りになど行かなかったであろう。
いつの頃からであろうか、エルサレムにある聖墳墓教会は巡礼者で賑わうようになったのであるが、まさかこの人たちは、いわゆる「墓参り」に行っているわけではなかろう。もしイエスの墓参りに訪れたい人がいれば、青森県の新郷村にあるキリストの墓を訪れるべきだ。そこではキリスト祭が現地の神主によって守られている。私もいつか訪ねたいと思っているが。
聖墳墓教会に巡礼する理由があるとしたら、それはそこが「空っぽ」であるという事実の確認であろう。では、墓が空っぽであるという事実は、われわれにとってどういう意味があるのか。イエスは復活したのだというなら、それが一番良いのだ。あるいは、神であるイエスは決して死んだままではないと考えるか。復活というどう考えてもあり得ないことを信じないとダメだというわけではない。イエスは十字架で死んだままではないと、そこに精神的な意味を見いだすというなら、それも立派な受け止め方だ。
弟子たちが遺体を墓から盗んでいったことにしたというのは、全く陳腐極まりない。しかし、そのようなうそを兵士たちにつかせた祭司長や長老たちが、やがてキリスト教徒になったとは考えづらいので、もはや彼らのことは思い切って放置でよいであろう。そのように言いたいのなら、40年といわず、100年でも、1000年でも言わせておけばよいのである。どうせこちら側にしても、イエスが復活したのだと説明はできたとしても、実証など不可能なのだ。
いやいや、2000年後も世界中にキリストの教会が存在している、それがイエスの復活の証拠なのである。と言いたいところだが、私には言いたくても言えない。そういう説明は敗北に過ぎないようにさえ思う。なぜかと言えば、残念であるが、キリスト教会がイエス・キリストの教えに忠実であったとは言い難いし、それは今も継続中だと思うからであるが、いかがであろうか。
不思議なことに、キリストの復活はあったのだと説明するよりも、むしろ、キリストは文字通りには復活しなったかもしれないけれども、思想的に、あるいは精神的には復活し、今日の世界に生き続けている!と主張することに、今日の教会は結構なエネルギーを費やしているように思う。特にこの日本においては、そういう傾向が強いのではないか。キリストの復活の意味を一生懸命に伝えようとしている、その思いと熱心さには尊敬を感じてはいるのであるが、何かむなしい気持ちもある。
復活は、ユダヤ人が言い広めたように「なかった」ことなのだろうか。ハッキリ言って、そんなことはかけらも気にする必要はない。イエスは復活したと信じられる人にしか、信じることなど不可能なのである。イエスの復活にどういう意味を見いだそうが、信じられない人の心には何も響かないのだ。
そんなことよりも、イエスの言葉や行動がどれほどに善と愛に満ちていたのかを語る方が、有益ではないだろうか。キリスト教とはイエスの復活を祝う宗教ではあるが、一方で信仰を持たない人にもある程度は人生の意味と意義を教えるものである。人々の入信を願って宣教するのか、イエスが実現しようとした善と愛のために宣教するのか。われわれの心は絶えず揺れ動いてゆく・・・。(終わり)
◇