「救い」(salvation)
救いは、贖(あがな)いという客観的事実を、主観的に実感することであります。シピーボ人は、救いは「生きるようにする」という意味だと言います。もし、罪の支払う報酬が死である(ローマ6:23)とすれば、救いは確かに命であります。その命は、永遠に続く命というだけでなく、永遠に続く性質をもって今すぐ始まる命なのです。「私の言葉を聞いて、私をお遣わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、・・・死から命へと移っている」(ヨハネ5:24)。
サン・ブラス人は、救いを神学的な面から明確に説明しています。「悪いことをしたことに対する助けを受ける」と言うのです。この助けというのはどんな助けでもよいというのではなく、罪を犯してしまった魂への助けです。スーダンのンゴク・ディンカ人は、救いを「助け」と表現します。しかし、それは「魂に関する助け」(逐語的には、息に関する助け)です。救いというのは、従って「魂・助け」であります。
カバラカ人は、救いに関しては個人的な触れ合いを強調し、救い主のことを「私たちの手を取ってくださる方」と言っています。この表現は美しいだけでなく、霊的な真理を表しています。イエスは、地上での働きの間ずっと、個人個人の必要に応える時間をいつも持っておられました。また今でも、「私たちの手を引いて」三位一体の神との交わりに導いてくださるのです。
これまで見てきたように、救いは単なる逃避以上のものです。逃避の神学では、魂は決して満足しません。キリストが与えてくださるのは、決して現実からの逃避ではなく、生きる力なのです。出口ではなく登り口、保護ではなく力です。
「和解」(reconciliation)
和解というのは、贖いと救いという一大事業への神の関与を物語っています。これは、パウロがコリントの信徒へ「神はキリストによって世を御自分と和解させ」(2コリント5:19)と書いている良きおとずれなのです。和解という言葉で、人間が(神に)反逆している存在であることと、神が主導権を握っておられることが分かります。そして、これこそがキリスト教の教えが他のすべての宗教と異なっている点です。キリスト教だけが罪の問題を真剣に取り上げ、それが一体何なのかを認めているのです。すなわち、罪とは物事に対する不適応ではなく、神に対する反逆と考えているのです。この世とご自身を和解させるために主導権を握っておられるのが神であるとしているのは、キリスト教だけです。
アラスカのバロウに住むエスキモーは、和解を単純に「もう一度友達になる」(仲直りする)と表現しています。すなわち、「神はキリストによってこの世と仲直りされた」と言うのです。スーダンのウドゥク人は、同じことを「会って、一緒に指を鳴らす」というちょっと面白い慣用句を使って表現しています。この表現は、お互い会ったときに指を鳴らすというウドゥク人の習慣から来ています。握手をする代わりに、彼らは親指と中指を伸ばして指を鳴らすのです。
しかし、これは友達に会ったときだけにします。相手に何か逸物(いちもつ)があるときには、お互いにこのように認め合うことをしません。それと同じで、人は生まれながらに神の敵であって、神と指を鳴らすことを拒んでいるのです。しかし、神が人と和解するために来てくださり、イエス・キリストを通してご自身との交わりに戻してくださったのです。今や、人と神は会って「一緒に指を鳴らす」ことができるのです。
ラオスの黒タイ人は、ちょっと違った譬(たと)えを使います。彼らは和解は「角(かど)を擦(こす)り落とす」ことにあると言います。これは、社会的に受け入れられることを言っているわけではなく、もともと合うはずの2つの物体の角を削って、ぴったり合うようにするという意味です。人は、罪の故に神の計画と交わりにぴったりはまることができなくなりました。罪はその人を変形させてしまい、その人の人格の中で醜い部分が目立って成長してしまうのです。悪の角は擦り取り、神との和解を得ることで、この世に対する神の永遠の計画に、ぴったり当てはまることができるようになるのです。
*
【書籍紹介】
ユージン・ナイダ著『神声人語―御言葉は異文化を超えて』
訳者:繁尾久・郡司利男 改訂増補者:浜島敏
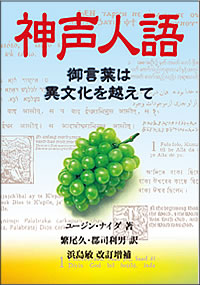
世界の人里離れた地域で聖書翻訳を行っている宣教師たちと一緒に仕事をすることになって、何百という言語に聖書を翻訳するという素晴らしい側面を学ぶまたとない機会に恵まれました。世界の70カ国を越える国々を訪れ、150語以上の言語についてのさまざまな問題点を教えられました。その間、私たち夫婦はこれらの感動的な仕事の技術的な面や、人の興味をそそるような事柄について、詳細なメモを取りました。
宣教師たちは、未知の言語の文字を作り、文法書や辞書を書き、それらの言語という道具を使って神の言葉のメッセージを伝えるのです。私たちは、この本を準備するに当たって、これらの宣教師の戦略の扉を開くことで、私たちが受けたわくわくするような霊的な恵みを他の人たちにもお分かちしたいという願いを持ちました。本書に上げられているたくさんの資料を提供してくださった多くの宣教師の皆さんに心から感謝いたします。これらの方々は、一緒に仕事をしておられる同労者を除いてはほとんど知られることはないでしょう。また、それらの言語で神の言葉を備え、有効な伝道活動の基礎を作ったことにより、その土地に住む人々に素晴らしい宝を与えられたことになります。その人たちは、彼らの尊い仕事を決して忘れることはないでしょう。
本書は説教やレッスンのための教材として役立つ資料を豊富に備えていますが、その目的で牧師や日曜学校教師だけのために書かれたものではありません。クリスチャン生活のこれまで知らなかった領域を知りたいと思っておられる一般クリスチャンへの入門書ともなっています。読者の便宜に資するために3種類の索引をつけました。①聖句索引、本書に引用されている聖書箇所を聖書の順に並べました、②言語索引、これらのほとんど知られていない言語の地理上の説明も加えました、③総索引、題目と聖書の表現のリストを上げました。
ユージン・ナイダ
◇