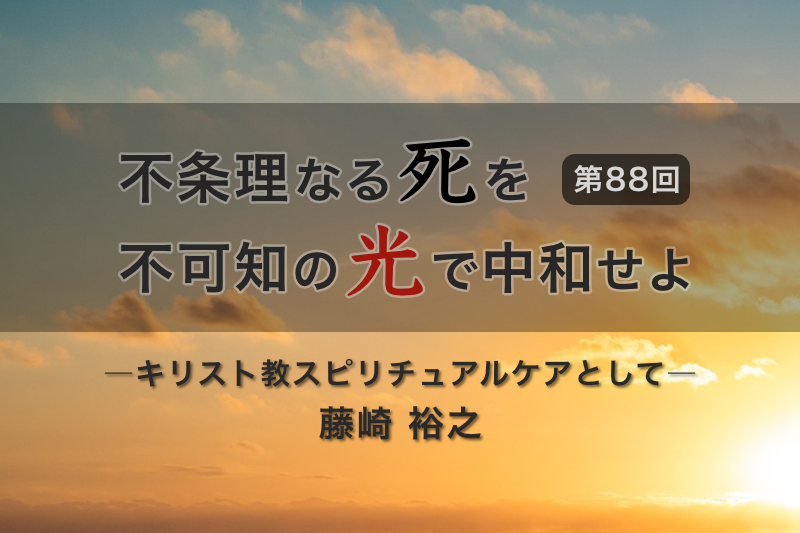
不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(88)
キリスト教徒は自らの十字架を背負わなければならない。自らの十字架であって、イエスが背負った十字架ではない。などということは口にすべきではない。なぜかと言えば、イエスの十字架と自らの十字架は別物だと考えるとしたら、それは恐らく、イエスと自分を引き離すことになるからだ。イエスが背負ったほどの十字架ではないとしても、イエスと無縁な十字架になってはならないのだ。
イエスは自らの受難を弟子たちに告知した。大変に有名な箇所だ。受難告知だと教わったが、実際には復活についても話されていることを見逃してならない。このように書くと「受難と復活、どっちがメインですか」と聞かれるが、受難のない復活はないし、復活のない受難もあり得ない。
復活がなくても「神の子の自己犠牲」ならあり得るのではないかと思われがちだが、果たして十字架の死は自己犠牲であったのか断定できない。イエスは、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺されると語ったのであって、自ら進んで犠牲になったとは言い難いような気もする。
聖書を区切り区切りで読んでいると、ついつい全体の流れを見失うことがある。この場面は、山上の変容の前に位置している。イエスがペトロ、ヤコブ、ヨハネを連れて高い山に登り、そこでこの世のものとも思われないほどに光り輝いたという出来事である。素直に読めば、神の栄光に包まれ、まさに神秘をまとったということになる。すると、雲の中から「これは私の愛する子。これに聞け」という声が響きわたったのである。
この出来事の後、イエスは3人の弟子を連れて山を降りるのであるが、その途中でこのように告げている。「人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならない」と。つまり、山上の変容は死者の中からの復活が先取りされているのである。
このように受難告知から山上の変容へとその流れを見ていくと、やはり復活がメインなのではないかと思える。しかもそれは、ただ単に死者が復活するということではなく、光り輝く姿になって復活するということが重要なのであって、来たるべき時にわれわれ自身もよみがえるということが先取りされているのである。そうでなければ、われわれ自身が十字架を背負う意味がなくなるからだ。
さて、受難を告知するイエスの言葉を聞いたペトロは、イエスを脇に連れていき、いさめ始めた。イエスのどの発言についていさめたのか。ずっと、イエスが排斥されて殺される、つまり十字架の受難についてだと理解していた。しかし、よく考えてみると、イエスが受難死することなのか、あるいは祭司長たちから排斥されて殺されることなのか、はたまた復活することなのか、三通りの理解の仕方があることに気が付いた。恐らく、これら全てが含まれるのであろうが、私が興味あるのは、ペトロがどう理解していたかということだ。イエスの言葉を聞いたペトロの心境を知りたいわけである。もちろん、それは不可能であるのだが。
イエスが死んでしまう、そんな事実を語ってほしくない。ユダヤの宗教指導者たちがイエスを迫害して殺してしまう、そんな恐ろしいことは言ってほしくない。死者が復活する、そんなおとぎ話的な話は聞きたくない。さて、ペトロはどう思っていたのであろうか。
ユダヤの宗教指導者への不満や批判というのは、当時の人々にとってもある程度は共感し得るものだったのかもしれない。まあ、どの時代もそういうものだ。だからと言って、彼らが人をあやめる存在だと宣言するのは、言い過ぎだといえなくはない。事実としては、イエスの十字架において現実のことになるのではあるが、それでもイエスの発言が火に油を注いだような気もする。ペトロには、そういう危機感があったのかもしれない。
師が自らの死を予告するというのは、弟子にとってはつらいことだし、それを否定するのも弟子としてのお作法なのだといえば、その通りだろう。「私たちの前でそんな弱気なことを言わないでください」的なことは、私も言いかねない。
死者が復活する。これは誰が聞いても不思議というか、付き合いきれない話ではある。付き合いきれない話を繰り返し聞かされるのが、キリスト教の真髄ではあるが、確かに誰もがちょっと戸惑う。恐らく、その戸惑いがなくなったときこそ、信仰的な危機が訪れるのである。(続く)
◇