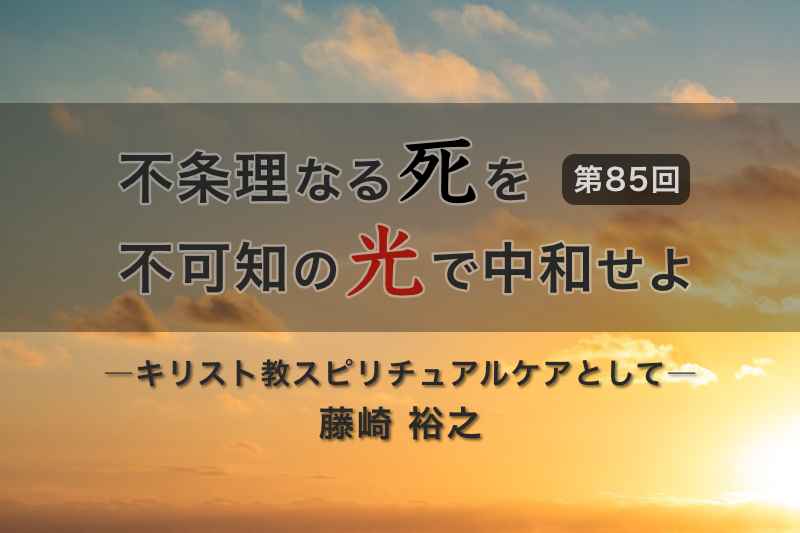
不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(85)
※ 前回「私の名を使って(その2)」から続く。
イエスいわく、「私たちに逆らわない者は、私たちの味方なのである」。正直なところ、これは相当に理解が難しい言葉だと思う。イエスが言われる「私たち」というのは、イエスと弟子たちのことだろう。それを拡大解釈して「教会」と読み替えるのは、かなり無理筋だとは思う。ではあるが、ここを糸口にして、いろいろと考えてみることにしよう。
日本において、キリスト教に触れたことのある人はかなり多いし、何らかの理由で教会に関わった人も相当にいると思う。以前にも書いた記憶があるが、私は教会付属の幼稚園の出身である。当時、幼稚園の教諭は全て教会員だった。恐らく教会員になることが条件だったのだろう。ただ、教諭だった人がその職を辞めてからも教会から遠ざかることはなかったので、今とは様子が違っていたようにも思う。
幼稚園を辞めると同時に教会からも姿を消すというのは、こちら側としては相当にショックではある。一度でもキリスト教に触れてもらえたのには意味があったのではないか、という意見もある。キリスト教主義の施設団体を運営しているのであれば、職員への宣教というのは大きな目的である。キリスト教主義を標榜してきた施設団体では、子どもたちや保護者、また利用者に聖書の話をしたり、賛美歌を歌ったり、お祈りをしたりと、いろいろなことをする。その職務を遂行するために、キリスト教信者ではない職員が携わることもある。
とは言えだ! キリスト教に触れた人や関わった人、あるいは今もうっすらと触れたり関わったりしている人が、キリストのシンパだという言い方は安易なのかもしれない。こういう問題を考えると、私としては、何とも分からなくなってしまって、いったいどういう線引きをするべきか不安にさえ思えるのだ。
端的に言えば、罪というものはキリストへの逆らいなのだ。正教会では罪を告白して赦(ゆる)しを頂かないと、ご聖体はもらえない。ご聖体を拝領できないと困る。故に私たちはとにかく「痛悔」をする。それはそれでかなりシンドイのだ。自分自身にどういう罪があるのか、つまり、どういうキリストへの逆らいがあるのかを、自分に問うのだ。痛悔というものは、教会に行って「パっ」と出てくるものではない。
確かに、私自身にはキリストへの逆らいがある。それはそれで自覚があるから、それで良しではある。では、世の人々には、どういうキリストへの逆らいがあるのだろうか。いや、他者について詮索するのはふさわしい行動ではないだろう。
結論から言えば、私の目にはキリストに逆らわない人というのは皆無である。しかし、キリストの目にはそうではないのだろう。そこら辺をしっかり自覚しないで、誰がキリストの敵であるとか、味方であるとかを論じるのは、危険に満ちているように思う。キリストに逆らわない人というのは、確かにいるのだ。その人が信者かどうかはあまり意味がないのかもしれない。
イエスの名を使って奇跡を行う人たちがいた。イエスはその人たちを良しとされた。たとえイエスや弟子たちと行動を共にしていなくとも、それらの人々は味方であると言われた。イエスの名による奇跡、それはどこまでも他者優先であって、決して自己の名を高めるものではない。しかし、他者優先であるということと、自己優先であるということは、ある意味で矛盾はしないのだ。イエスの名によって行動するということは、そこに「自分」という存在がなければならない。自己の名を高めるためではないが、自分自身が神に向かって高められる者であらねばならないのだ。
イエスに従うことは、決して滅私ではいけない。なぜならば、キリストは自己を犠牲にして死んだが、復活された方であるからだ。私たちが滅私奉公で自分自身が死んだままであったならば、それこそがキリストに逆らう道に他ならないのだ。
私たちは死んだままではいけない。復活しなければならない。奇跡とはそういうものなのだ。イエスの名による全ての行為が復活という奇跡へと向かう道程だ。だからこそ、「私たちに逆らわない者は、私たちの味方なのである」というイエスの言葉が、意味をなしてくるのではないだろうか。(終わり)
◇