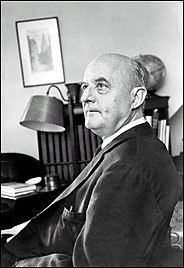
今回は少し神学的なコラムを書こうかと思います。20世紀の米国のプロテスタント神学者で最も政治・社会に影響力を持っていた人がラインホルド・ニーバーだと言われます。ドイツの神学者、ボンヘッファーや米国の市民権運動の指導者であったキング牧師などに強い影響を与えたとも言われています。
ニーバーの書いた書物に『道徳的人間と非道徳的社会』というものがあります。ニーバーが主張していたことは、人間というものは、個人としては利他的に生きることが可能であるが、人間が集まる団体や社会などの集合体になると、自己の利益を優先するようになる、ということであったと思います。個人的な付き合いであれば、友情を育むことができるが、これが団体同士とか、国同士とかになったりすると、自らの利益を優先せざるを得なくなって、対立していく構図になるというようなことを言いたかったのだと思います。
だから、政治や国際関係においては、ナイーブな倫理道徳観は通じない、そのため現実的路線で考えて軍隊を必要とするし、軍備を拡充しておく必要があるのだという考えになります。こういった考えを持っていたため、彼のことを現実主義的キリスト者と呼んだりします。
ニーバーは、とかくナイーブに物事を考える傾向にあった当時のキリスト者に、現実的悲観的人間論を示して、原罪というものが人間にどのように浸透しているかを、2回の世界戦争を背景に神学的に展開していきました。
これとは対照的に、前回取り上げたスイスのカール・ヒルティはもう少し楽観論に立っていて、愛の国を造らなければならない、という内容のことをここかしこで語っています。私たちが生かされているのは、愛の種をまくためである、できる限り多くの愛の種をまきなさい、ということを言います。ヒルティはまだ世界戦争を経験していなかったからかもしれません。
ニーバーは、現実的路線を取らざるを得なかったのでしょう。私はニーバーの中にも、ヒルティの中にも真理を見いだします。ジョン・ウェスレーは「罪の悲観論と恵みの楽観論」という言葉を使って、私たちの生を表現しました。
◇